株式会社設立の手続き・登記
Incorporation
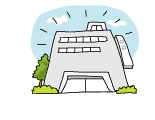
「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「節税をしたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。
株式会社設立の手続き・登記について
平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。
会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。
新しい会社法によって、今までアイデア・ノウハウはあるけども資金面・人材面から株式会社の設立を見送られていた方や、個人で事業されていた方などが、容易に株式会社を設立することができるようになったといえます。
会社法は、手続き面でも旧商法に比べ、スピーディーに設立手続きを進めることができるよう改正されました。
例えば、旧商法では設立登記の申請に際に必要だった金融機関が発行する『資本金の払い込みを証明する書面(資本金払込保管証明書)』が、会社法では必要ではないため、金融機関に証明書の発行を依頼をする必要がありません。設立までに係る時間を1週間は短縮できます。
株式会社の設立にあたっては、少なくても次の各事項の内容を決め、どのような株式会社を設立するかを決める必要があります。
なお、会社法では、旧商法に比べ、中小企業や大企業などの実情にあった株式や機関(株主総会・役員など)を格段に自由につくることができます。
● 商号・本店
株式会社の名称である商号と本拠になる住所である本店の所在地を決めます。
商号には、必ず『株式会社』という文言を商号の前か後に付ける必要があります。
商号は、本店の所在地に全く同じ商号をもつ株式会社が既に登記されていなければ、一定のルールに従い自由に登記することができますが、すでに存在している知名度の高い名称や、近隣に同一・類似の商号をもつ同業を営む会社がある場合は、トラブルになる可能性があるのでご注意ください。
● 目的
株式会社の事業目的を決めます。株式会社は目的の範囲でしか活動できません。
事業目的の数に制限はありませんので、将来的に行う可能性がある事業については登記したほうがいい一方で、やみくもに事業目的を増やすと、何をメインとして活動する株式会社か分からないイメージを与えますので、バランスが大事です。
許認可が必要な事業については、目的に当該事業内容がないと、許認可を受けることができないので要注意です
● 出資者(発起人)・出資額・資本金の額
株式会社に資本を出資し、設立を参画する発起人と、発起人の出資割合、事業の元手となる資本金の額を決めます。出資者である発起人は、1人でも複数人でも全く問題ございません。
出資者・割合は、株式会社の経営権・支配権の割合に直結することのほか、出資者・割合によって税の取扱いが異なることもあります。
また、資本金の額は、税の取扱いや、許認可の要件、下請法、独占禁止法など様々なことに影響を及ぼすので、その額を決める場合は要注意です。
● 機関・役員、役員の任期
株式会社を構成する機関と役員、その役員の任期を決めます。
役員は取締役1名のみでも株式会社を設立することができます。取締役3名と監査役(または会計参与)1名の計4名以上の役員を置く場合は、取締役会という機関を設置できます。
役員の構成によっては、税の取り扱いが異なる場合があるため、注意が必要です。
役員の任期については、原則は約2年ですが、全ての株式の譲渡を制限する非公開会社に限り、約10年まで任期を伸長することができます。
● 事業年度
株式会社の事業年度を決めます。事業年度の末日が決算日となります。資本金の額が1000万円未満の場合は、設立後2期分の消費税の納めなくてもいい特例を受けることができるので、ご注意ください。
設立する株式会社の内容を大幅に自由にすることができる一方で,安易に設立してしまうと,設立後に税金で損をしたり,助成金が受けれなかったり,許認可が受けれなかったり,法的トラブルが起きてしまうことなども少なくありません。
株式会社を設立する際には,専門家の意見を聞かれた方がいいでしょう。
当事務所では、株式会社の設立手続きを登記申請を通じて全面的にサポートさせていただきます。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
なお、[1]ご依頼いただいてから、[6]登記申請までにかかる期間は,最短で1日,余裕をみていただいて1月程度です。
(事前商号調査なし)
代表者印は会社設立後,会社の実印にあたるものになります。
ご捺印いただきましたら,当事務所で公証役場に出向き,定款について公証人の認証を受けます。
公証人は法務局または地方法務局に所属する公務員です
また,その他設立に必要な書面を当事務所が作成し,役員(取締役・代表取締役,監査役など)全員のご印鑑および代表者印を押印していただきます。
登記を申請した日が株式会社の「設立日(誕生日)」になります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」,「代表者印の印鑑カード」,「代表者印の印鑑証明書」などをお渡しします。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
設立される会社の内容によっては,別途ご用意いただく書面等もございます。
- 発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)
定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3月以内のものをご用意ください。 - 代表取締役の印鑑証明書(1通)
法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの) - 会社代表者印
- 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
- 役員全員の印鑑証明書(各1通)
法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
資本金が1000万円以下で,かつ現物出資がない場合
このほか登記には15万円の登録免許税,公証人に支払う約5万円の手数料が必要です。なお,当事務所は定款を電子データで作成するため,4万円の収入印紙をご負担いただく必要はございません。
資本金が1000万円以上で,かつ現物出資がない場合
このほか登記には登録免許税(資本金の0.7%,ただし最低15万円),公証人に支払う約5万円の手数料が必要です。なお,当事務所は定款を電子データで作成するため,4万円の収入印紙をご負担いただく必要はございません。
株式会社設立のために必要な定款の認証を受ける手続きについて、当事務所では定款を電子データで作成するため印紙税法上の課税文書の適用を受けず、定款を書面で作成した場合にご依頼者が実費で負担する印紙代4万円のコストダウンが可能です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします