相続放棄
Inheritance waiver
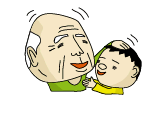
当事務所では,負債などのマイナスの遺産を相続された方に、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成し、プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しない相続放棄の手続きをお手伝いいたします。
相続放棄について
ご家族が不幸にも亡くなり,相続が始まると、被相続人(亡くなった方)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。
遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。
相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。
相続放棄の申述は、「相続の始まったことを知った時」から3箇月以内に、家庭裁判所に申述する必要があるので注意しましょう(民法第915条)。
「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が最も多いケースですが、その他「マイナスの財産があることを知った時」や「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」などがあります。
遺産分割協議(相続人間の話し合い)で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、負債を相続していないことを主張できません。負債から免れるためには、相続放棄が必要です。
遺産分割で一切のプラスの財産を相続しなかった方も、「相続を放棄した」という認識でいることが少なくありませんが、家庭裁判所を通した相続放棄をしない限り、負債を相続したものとして扱われます。
相続開始後、相続放棄申述前に、亡くなった方の財産を処分してしまったり、使用してしまうと、場合によっては相続放棄の申述を家庭裁判所で受理してもらえない可能性があるので注意しましょう。
限定承認という方法
プラスの財産(預貯金・不動産・株など)とマイナスの財産(借金・保証債務など)どちらが多いか分からず、相続放棄を決めかねる場合は、プラスの財産からマイナスの財産(借金・保証債務など)を弁済し、足りなければそれ以上弁済する必要もなく、余れば余った分を相続できる「限定承認」という方法があります(民法第922条-第937条)。
● 限定承認は、相続放棄と同様、「相続の始まったことを知った時」から3箇月以内に家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄と異なり、相続人全員が共同して申述する必要があります。
● 限定承認は合理的な相続の方法だと思いますが、手続きが煩雑なことからあまり利用されていないのが現状です。
誰が相続人になるか、また相続分はそれぞれどの程度あるのかという問題は,離婚,養子縁組,相続放棄や相続人にあたる者の死亡などにより,複雑になっているケースが少なくありません。お困りの場合は,まずはご相談ください。
当事務所では,家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成し、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
ご依頼いただいた場合は,次のような手続の流れになります。
ご依頼者にご用意いただくもの
ご依頼者の方は,相続放棄の申述をするために次のものをご用意ください。
- 被相続人(亡くなった方)が死亡したことがわかる戸籍・除籍謄本
戸籍をおいた市区町村役場で取得できます - 被相続人の除住民票の写し
被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます - 相続放棄される方の現在の戸籍謄本
各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます
- 負債等の内容がわかる資料
債権者からの請求書・通知書、負債内容がわかる契約書・資料等をご用意ください。
- 土地・建物の登記事項証明書 法務局で取得できます
- 車検証 お手元にご用意できる範囲で結構です。
- 株券等の写し お手元にご用意できる範囲で結構です。
- 通帳の写し等 お手元にご用意できる範囲で結構です。
報酬・費用
当事務所の登記申請にかかる報酬は次のモデルケースをご参考ください。
相続放棄する相続人お一人につき
このほか相続放棄の申述には、印紙代800円と、郵便切手代(予納郵券)400円程度(管轄裁判所によって異なります)が必要です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
平日午前9時から午後6時まで受付けいたします
ご相談いただいた日または翌日(土日祝祭日除く)には回答いたします